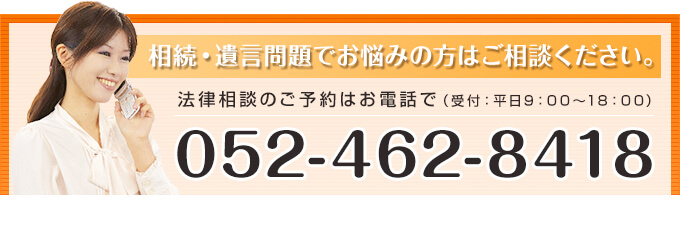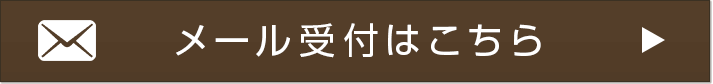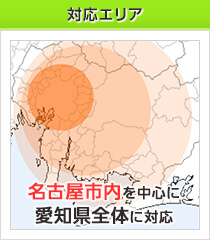遺贈に関するQ&A
Q:遺贈とは何ですか。
A:遺言により、無償で、自分の財産を他人に与えることをいいます(民法964条)。
遺贈は遺言者が一人でできる単独行為であり、遺言者の死後に効力が生じます。遺言者の死後に効力が生じる点で死因贈与と類似していますが、死因贈与は贈与を受ける相手方との契約である点で、単独行為である遺贈とは異なります。
Q:遺贈にはいくつか種類があると聞きましたが、どのようなものがありますか。
A:包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、遺産(権利及び義務を含む)の全部、または一定の割合の遺産を与える遺贈です。例えば、全ての遺産をAに遺贈する、遺産の3分の1をBに遺贈する、といったものです。
これに対して特定遺贈とは、特定の財産を与える遺贈です。例えば○○番地の土地を遺贈する、○○銀行の預金を遺贈する、といったものです。
Q:遺言で財産をあげたいのですが、相手は誰でもよいのですか。
A:遺贈を受ける人を受遺者といいます。
受遺者は相続人でも、相続人ではない第三者でも構いません。自然人に限らず法人も受遺者になることができます。そのため、個人だけでなく、社会貢献としての一環として慈善団体やNPO法人などの団体に対しても遺贈をすることができます。まだ生まれていない胎児も、相続では生まれたものとみなされますので受遺者になることができます(民法965条、886条)。
Q:相続人以外に財産を遺贈したいのですが、気をつけるべき点はありますか。
A:公正証書遺言にすること、遺留分を侵害しないようにすること、相続人の感情へ配慮することの3点に気をつける必要があります。
近年、社会貢献活動の一環として、お世話になった介護施設やNPO法人、その他慈善団体へ遺贈する方が増えています。その際注意すべき点は主に4点です。
①公正証書遺言にすること
遺言は自筆証書遺言でも可能ですが、自筆証書遺言の場合、形式面で法律の要件をみたさず無効になったり、長い年月の間に紛失してしまったり、偽造や変造される危険があります。それらの危険を防止するために、公正証書遺言によることをお薦めいたします。
その際には、遺言執行者を指定しておき、遺言内容がスムーズに実現できるようにしておく必要があります。この遺言執行者については弁護士などの第三者を選任するほうが良いでしょう。親族では感情的対立により円滑な執行ができない可能性があるからです。
公正証書遺言については遺言作成に関するQ&Aをご覧ください。
②遺留分を侵害しないこと
遺言によってどのように財産を処分するかは遺言者の自由ですが、最低限相続人に残さなければならない割合(遺留分)があります。遺留分を侵害する遺贈は、遺留分を侵害する範囲で無効になる場合があり、せっかく遺贈しても遺言者の希望どおりにならない可能性もあります。
そのため、相続人以外の第三者へ遺贈する場合には相続人の遺留分に配慮する必要があります。遺留分についての詳細は遺留分についてのQ&Aをご覧ください。
③相続人の感情に配慮すること
第三者への遺贈については、相続人からすれば本来相続できるべき財産が減ることを意味します。そのため感情的な対立を招く虞があります。そこで、遺言の付言事項として、どうしてそのような遺贈をしたのかについて具体的な遺言者の思いを記載しておく、生前に相続人にしっかりと思いを伝えるなどの対策が対策が必要です。
④受遺者の意向を確認すること
財産の内容によっては受遺者になる予定の方や団体が拒否する場合もあります。現金や預貯金であれば特に問題はないと思いますが、例えば不動産については受遺者で有効活用できなければ、いらないと言われてしまいます。受遺者にとってありがたい財産であるかどうかは事前に確認をしておく必要があります。
Q:最初は長男に相続させ、長男亡きあとは孫に相続させたいのですが、可能でしょうか。
A:いわゆる後継ぎ遺贈はできません。
遺言の効力が発生した後、受遺者が死亡した場合、遺言者の指定する者に遺贈の目的物を相続させることを後継ぎ遺贈といいます。このような後継ぎ遺贈は権利関係が不安定になることから無効であると考えられています。
もっとも、このような場合には遺贈ではなく、家族信託(民事信託)を活用することで目的を達成することができます。
家族信託については民事信託(家族信託)に関するQ&Aをご覧ください。
Q:「遺贈する」と「相続させる」とではどのような違いがありますか。
A:登記、農地法の許可、賃貸借、代襲相続といった場面で違いがあります。
「遺贈」の場合、遺贈の効力発生と同時に権利が受遺者に移転しますが、権利の移転を第三者へ対抗するためには登記などの対抗要件を備える必要があります。
一方「相続させる」の場合、原則として遺言者の死亡時に直ちに当該相続人に承継され、権利の移転については第三者へ登記などの対抗要件なくして対抗できるとされています(最高裁平成14年6月10日判決)。
登記については、遺贈の場合、受遺者と相続人の共同申請になりますが、「相続させる」の場合は、当該相続人の単独申請で足ります(不動産登記法27条)。
農地法上は、「遺贈」の場合は知事の許可がなければ権利移転しませんが(農地法3条)、「相続させる」の場合は権利移転に知事の許可は不要です(最高裁昭和52年7月19日判決)。
遺産が賃借権であった場合、「遺贈」の場合は賃貸人の承諾が必要ですが(民法612条)、「相続させる」の場合は賃貸人の承諾は不要です。
「遺贈」の場合、受遺者が遺言者の死亡以前に亡くなった場合には遺言の効力は生じません(民法994条1項)。「相続させる」の場合は原則として遺言の効力は生じませんが、遺言者が代襲相続人その他の者に相続させる意思を有していたといえる場合には遺言は有効となります(最高裁平成23年2月22日判決)。
Q:遺贈を断りたいのですが、できるでしょうか。
A:遺贈の放棄ができます。
ある特定の財産についての遺贈(特定遺贈)であれば放棄することができます(民法990条)。また、遺贈の対象である財産が複数ある場合に一部だけ放棄することもできます。
そして、遺贈を放棄した場合には遺言者の死亡にまで遡り効力が生じますので、遺贈は始めからなかったことになり、遺贈の対象であった財産は遺産に含まれることになります。
遺贈の放棄については、相続放棄とことなり期間制限はないので、いつでも放棄することができます(民法986条1項)。これに対して遺贈義務者である相続人や利害関係人は受遺者に対して一定期間内に遺贈の承認または放棄をするよう催告をすることができ、その期間内に受遺者が意思表示をしない場合には、遺贈を承認したものと扱われます(民法987条)。
なお、包括遺贈の場合には相続放棄(915条以下)が適用されます。
Q:遺贈を受けた場合、税金がかかりますか。
A:受遺者には相続税がかかります。